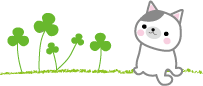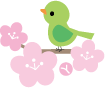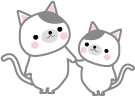祖母のあいに関して、思い出したことがある。なんとも、バカバカしい話だが。
2020年歳末。
アメリカの野球で、誰でも知っているベーブ・ルースのバットが、ニューヨークの「クリスティーズ」のオークションにかけられ、60万ドルで落札された。(2020年12月16日)
現存するベーブ・ルースのバットでも、もっとも古い2本のうちの1本という。
同じ時期、ヤンキースで活躍したルー・ゲーリックのユニフォームは144万ドル(約1億4880万円)。
詩人の鮎川 信夫は、少年時代にベーブ・ルースを見たという。東京の球場で。
私は、仙台の八木山の球場でベーブ・ルースを見た。
ベーブ・ルースがバッターボックスに立つと、満員の観衆が異様な興奮につつまれたことを覚えている。
初来日したヤンキースが、日本で当時唯一の職業野球チーム、「読売巨人軍」を相手にした野球を見たのは、自分でも信じられないのだが、むろんウソではない。
幼い私は、祖母の西浦 あいにつれられて、この歴史的な野球を見に行った。
生まれてはじめて野球を見たのだから、野球のルールについて何ひとつ知らない。ただ、ベーブ・ルースを見たのだから、当時、選手として出場した、ルー・ゲーリックや、沢村投手や、のちに名監督になる、若林、水原、三原などのプレイも見ていることになる。
試合が終わったあと、ファンが総立ちになってベーブ・ルースを迎えた。たちまち、ファンたちが群がってサインを求めた。
それを見ていた祖母は、私をシートにすわらせて、
「ここで、待っていな。動くんじゃないよ」
祖母のあいは、そういうと、韋駄天のようにその群衆のなかに走っていった。その敏捷さに私は驚いた。
しばらくして、あいが戻ってきた。
なんと、ベーブ・ルースのサインをもらってきたのだった。
日本のファンの多数は、サイン用の紙をもってベーブ・ルースにサインをもとめたと思われる。あいは、サイン用の紙をもっていたわけではない。走りながら、たまたまもっていた御簾紙か何かをつかみだして、まっしぐらにベーブ・ルースの目の前で振りたくったらしい。ベーブ・ルースは、気がるにサインしてくれたという。
このときあいがせしめたベーブ・ルースのサインは、神棚の隅に押し込まれて、我が家の宝物になったが、やがて忘れられた。小学生の私は、祖母の意外な行動力が心にきざまれた。
このサインは、1945年3月の大空襲で焼けた。毛布1枚とわずかな食料だけもって、猛火のなかをにげまどったのだから、ベーブ・ルースのサインなど、持ち出せるはずもなかった。今になってみると、ちょっと惜しい気もする。
このブログを書いているうちに、私が「お祖母さん子」だったことから、ベーブ・ルースのサインまで思い出した。
--少年時代 塩釜編 完--