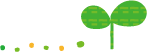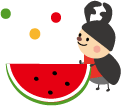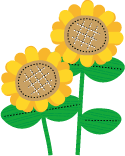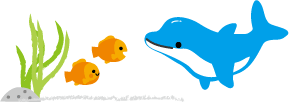仙台弁で、オボンコということばがある。私は、級友のひとりから、
おめはぁ、オボンコだかんな。
といわれた。先生に贔屓されている、という意味だった。私は、自分が担任の先生に特別に贔屓されているのだろうか。そういわれてみると、同学年の女子クラスの先生たちも、私の名前を知っていたようだった。
もう、退職まぢかだった内馬場先生、40代で、結婚しないまま、小学校の教員を続けていた沢田先生も、声をかけてくれるようになっていた。
級長になった生徒なので、職員室で、先生たちが、生徒のことを話したところで不思議ではない。
しかし、私は、「オボンコだかんな」という言葉に、はじめて自分が周囲からどう見られているのか意識するようになった。
小学3年生の子どもの内面に、なぜか深い変化が生じた。
それまでの、平穏無事な世界から、不意に、すべて無関心、あるいはささやかな差別からできている別の世界に落ち込むようなことがどうして起きるのか。
私の妹の純子は、小学校に入った。
当時のクラスは男女組という「男女共学」のクラスはあったが、女性の教員が男女組の担任になることはめずらしかった。こんなところにも、当時の教育の封建的な空気がうかがえる。
純子の担任は、これも柔道5段の大浦先生だったが、かなり厳しいスパルタ教育だったらしい。
おとなしい純子は、自分の担任だった小学校の先生たちに特別な感情を持っていなかったが、小学校教育はひどいものだったという。
純子は、初老の内馬場先生、40代の女性教員、沢田先生たちに教えられたが、何かにつけて、兄(耕治)に比較されるので、小学校の先生たちにひそかな恐怖をもつようになったという。
私は、内馬場先生、沢田先生たちに可愛いがられた。
小学3年生になった。
担任は彦三郎先生。この先生の思い出はほとんどない。じつは先生の姓が佐藤だったか、鈴木だったか、もうおぼえてもいない。
彦三郎先生の思い出もほとんどない。
当時の小学校教諭、とくに中年から上の世代の先生たちは、きまって鼻下にチョビひげを貯えていた。彦三郎先生は柔道5段。チョビひげのせいで、威厳があった。同じ3年の女子クラスの担任だった大浦先生がやはり柔道5段で、ふたりとも県の体育関係の先生として有名だったらしい。
先生のほうも、私にまったく関心がなかったのではないか。父親が外国系の会社に勤務している家庭で、比較的にリベラルな家庭環境に育った子どもになど、関心を持たなかったのだろう。
彦三郎先生が直接、私を避けているとか無視しているわけではなかった。しかし、クラスにいる間、何か間接的な不安が自分のまわりに立ち込めている。そのあらわれは、漠然としたものだった。ただ、彦三郎先生の視野に私は入っていない。
小学3年生の私は、そこにさだかならぬ、捉えどころのない、なにかにがい味を感じていた。
彦三郎先生は、いつも私を避けているようだった。先生が何か質問をする。生徒たちがいっせいに手をあげる。先生がその一人を指さす。生徒が答える。不正解の場合は、すぐ別の生徒が当てられる。別にめずらしい光景ではない。ただ、私が手を上げても、ほとんど当てられなかった。
はじめのうちは気がつかなかったのだが、やがて私は彦三郎先生にうとまれているような気がしてきた。
おとなしい生徒だったから、めだたなかったわけではない。むろん、反抗的な生徒だったとも思えない。
ただ、学校で彦三郎先生と、直接、口をきいたおぼえがない。私は先生に無視されつづけた。
自分に何の過失のおぼえもなく、こちらから先生をきらっているわけでもないのに、何か取り返しのつかない違反を犯したのかも知れない。私は、不意にクラスの仲間たちから切り離されたようだった。
当然、成績が落ちた。