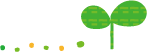私の家は、「真福寺」というお寺の斜め前だが、広瀬川に面した崖ッ淵に建っていた。すぐ後ろ側が、「真福寺」の墓地になっている。墓地としては、それほどひろくなかったが、それでも、墓場なのでほとんど人の姿を見ることはなかった。
この墓場のはずれから、住宅地がつづいていたが、その境界に、一本、白木蓮の古木が立っていた。江戸時代に植樹されたという。みごとな古木で、しっかりした枝を四方に張り出して、あたりの墓や、住宅をしたがえて、そびえ立っていた。
昼間でも、その老木の下蔭は暗く、その樹の周囲は光を遮断しているようにみえた。
ある日、私は、墓地の近くに住んでいた同級生のところに遊びに行った。たまたま、その子が不在だったので、墓地の中を歩いて帰ろうとした。
あの白木蓮の近くに誰か立っているようだった。
曇った日だったから、誰かが佇んでいたのか。私は、もう少し近くまで寄って行った。
大きな樹木の下に、みすぼらしい白衣の老人が佇んでいる。身の丈ほどの古びた杖を地面につけて、片手でにぎりしめている。
ややうつむき加減で、顔の表情はわからなかったが、顔の半分は、灰色のひげで覆われていた。とくに、顎から長いひげが垂れていた。私は、おもわずどきっとして、足をとめた。むしろ、足がすくんだといったほうがいい。
蓬髪で、みすぼらしい白衣だが、乞食ではない。仙人のようだった。
その老人を押し包むように、ほのかな光を発しているようだった。
このときの私が感じたものは、しいていえば、畏怖とでもいおうか。
この老人はこの世のものではない、という気がした。あたりは墓場なのだから死人が幽霊になって、この世をさまよっていても不思議ではない。しかし、幽霊ではなかった。
私は恐怖をおぼえたわけではなかった。ただ、それまで一度も経験したことのないことにぶつかった。何か、この世ならぬものに出合っている。何か超自然の現象が老人の姿を借りて、みじろぎもせず立ちつくしている。
正視してはならないものを見てしまった。全身がふるえた。私が見ているのは、一人の老人だったが、一人の老人の姿であって、同時にすべての老人の姿でもあった。私は、何かわけのわからない現象が、この老人の姿になって、出現したのだと思った。
私は、老人に気づかれないように、後ずさりをしながら、近くの墓に隠れるように身をかがめた。ほんの5秒ばかり経って、もう一度、木蓮に目をやった。
老人の姿はなかった。
小学生の見たあの老人は、その後一度も現れたことはない。
子どもの記憶なので、あくまで不確実なもの、不安定なものにすぎない。もの書きとして、それはよく知っている。それに、私の観察や、その情景を正確に表現できるとは思っていない。ただ、中国の絵に出てくる仙人のような老人だったことだけが心にのこった。
そして、このときのいいしれぬ畏怖は、それからも私から離れなかった。
しばらくして、あの老人は、木蓮の樹の精だったのだ、と思った。
現在、私が住んでいる家の玄関先に、木蓮が植えてある。毎年、春の気配がただよいはじめると、まっさきに純白の花が開く。2021年、すでに白頭翁と化した私は、その輝きが好きで、しばしば玄関先に立つ木蓮の下に立って、純白の花を仰ぎ見ることがある。
そして、あの老人の姿は、ひょっとして私自身の「現在」ではなかったか、とも思う。