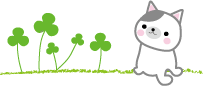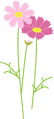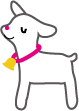1977年12月2日(水)
女優、望月 優子が亡くなった。
もともとは喜劇女優だったが、昭和29年、木下 恵介の「日本の悲劇」で「毎日コンク-ルの主演女優賞を受けてから、演技派の女優になり、昭和33年に、今井 正の「米」でブル-・リボン主演女優賞を受けた。
46年、参院選で、大量に得票して、参議院議員になったこともある。
私は、ム-ラン・ル-ジュ、古川 ロッパの一座にいた頃の望月 優子を見たことがある。慶応出身の作家で、「サンケイ」の記者、鈴木 重雄の夫人。三島 雅夫を中心に結成された劇団、「泉座」が旗揚げ公演に、ア-サ-・ミラ-の「みんなわが子」を選んだ。そして、翻訳を私に依頼してきた。
私の「みんなわが子」訳は戯曲の訳としては最低だった。稽古の段階で、私は、自分の翻訳が舞台では使いものにならないことを思い知らされた。
演出家、菅原 卓が手を入れた。この訳はのちに菅原 卓訳として「早川書房」から出ている。)この芝居に、望月 優子が出たので、口をきくようになった。ある日、稽古場で、望月 優子が私をつかまえて、
――中田さん、あんた、スタニスラフスキ-、読まなきゃダメよ。
といった。そばにいた千石 規子が、したり顔で、
――そうよ、そうよ。スタニスラフスキ-、読まなきゃダメなんだから。
私は、二人の女優に侮蔑をおぼえた。私はまだ演出家になる前で、この稽古場では、「みんなわが子」の翻訳をしながらできの悪いホンなので、みんなに迷惑をかけた青二才に過ぎなかった。
その青二才の目にも、このふたりの芝居はひどいものに見えた。
とくに、千石 規子の芝居はひどいものだった。
「みんなわが子」の初日をみにきた高峰 秀子が、千石 規子の芝居にあきれて隣りにいた女優と顔を見合わせて失笑していたことを思い出す。
私の「みんなわが子」の翻訳が、戯曲の翻訳としてはひどいものだった。セリフになっていなかった。なにしろ、菅原 卓が、面と向かって、
「中田君、腹を切りなさい」
とまでいわれたのだから。
冷静に見て、この芝居の失敗は、望月 優子、千石 規子がミス・キャストだったからと思っている。
この失敗から私は芝居の演出をめざすようになったのだから、望月 優子、千石 規子に礼をいわなければならないかも。
望月 優子は、最後には「日本の母」などと呼ばれる名女優になった。千石 規子は、黒沢 明の映画に、かならず出るようになった名女優になった。私は、このふたりの芝居を見るたびに、「みんなわが子」の演技を思い出したものだった。
もう一つ。
これも、新聞のオ-ビチュアリで、テレンス・ラティガンの訃を知った。
11月30日、ガンのため、バミュ-ダで死去。66歳。
オックスフォ-ド大卒。1936年、「泣かずに覚えるフランス語」で劇作家としてデビュ-。主な作品に「ウインズロ-家の少年」、「ブラウニング・ヴァ-ジョン」、「紺碧の海」などがある。映画のシナリオにも手を染め、「チップス先生さようなら」、「黄色いロ-ルスロイス」、「王子と踊り子」などを書いた。
67年以来バミュ-ダに住みつき、71年にナイトの称号を授けられた。
AP時事の記事で、戯曲のタイトルの訳はひどいし、これではテレンス・ラティガンが「戦後」のイギリス劇壇に与えた影響について何もわからない。
「泣かずに覚えるフランス語」はナイだろう。せめて、「楽に身につくフランス語」ぐらいでないと、喜劇かどうかもわからない。「深く、静かな青い海」を「紺碧の海」にしてしまうと、ラティガンの上品な世界が見えてこない。
私はひそかにラティガンの死を悼んだ。
もっといい戯曲を書いてくれればよかった人なのに。

1977年12月2日(水)
作家、海音寺 潮五郎、逝去。
海音寺 潮五郎、明治35年11月5日、鹿児島県大口市に生まれた。
1929年、「サンデ-毎日」の懸賞に「うたかた草紙」を応募。
1936年、「天正女合戦」で、直木賞。戦時中は、陸軍報道班員として、マレ-方面に派遣された。「戦後」は、1953年、「蒙古来る」、S29年、「平将門」、S35年、「天と地と」、など。
S43年、引退を表明。
昨年、NHKで、「風と雲と虹と」が放送された。
残念ながら、私は一度も海音寺 潮五郎を批評する機会がなかった。
ヴァレリ-ふうにいえば、こういう人たちは、二度死ぬのだ。一度は人間として、もう一度は有名な作家として。
まあ、人生いろいろだなあ。

1977年12月3日(水)
体調がわるい。風邪のため、咳がとまらない。めったに風邪をひかないのだが、今年は、どういうわけか、いちばん先に私が倒れてしまった。
今日、木更津で講演があるのだが、咳が出ると困る。
11時半、県立図書館、司書の竹内 紀吉君と駅前で会う。
竹内君も、私の咳を心配していた。「ロ-タリ-」で食事をしようと思っていると、そこへ、安東 由利子と石井 秀明がきてくれた。「南窓社」に寄って、私の本を10冊もってきてくれた。
食事をしているところに安東君がきてくれた。
今日の千葉駅は――国労、動労が、成田開港反対の遵法ストに突入したため、混乱している。私たちも予定を変更して、快速に乗った。
木更津着、1時半。すぐに会場に向かう。
参加者は140名程度。会場は、満員状態。YBC側としては、これほど多数が参加するとは思っていなかったので竹内君に謝ったという。
講演はうまく行ったと思う。しかし、途中で、咳が出たため、一時中断。
講演のあと、質疑応答のようなやりとり。
「私のアメリカン・ブル-ス」にサイン。わずかな部数しか用意しなかったので、すぐに売り切れてしまった。
安東君たちをねぎらうつもりで、駅前の喫茶店で話をする。
みんなと別れて、竹内君といっしょに、庄司 肇さんを訪問する。
庄司さんは、「日本キャラバンを主宰している同人作家。眼科の先生。気骨のある人だが、気さくにいろいろな話をしてくれた。
辞去したのは、8時過ぎ。
ストライキの影響で、夜もダイヤが乱れている。8時45分頃、やっと電車に乗れた。

1977年12月8日(月)
午後、本田 喜昭さんの奥さんが、千葉まで原稿をとりにきてくれた。恐縮した。
しかし、私自身がひどい風邪だし、家族そろって寝込んでいる状態なのだから、どうしようもない。
百合子までが寝込んでしまった。
「公明新聞」から原稿の依頼。大阪の友人、船堂君から電話。
夜、義母、湯浅 かおる、義姉、小泉 賀江が見舞いにきてくれた。
写真の現像。

1977年12月9日(火)
百合子、肺炎併発の疑いあり。
義兄、小泉 隆の診察を乞う。
「東和」から、「カブリコン・1」(ピ-タ-・ハイアムズ監督)の公開記念に、ITCのル-・グレイド郷が来日したので、パ-ティ-をやるという。
映画の批評をやっていると、ときどき思いもよらない招待を受けたり、来日したVipに紹介されたりする。
CICから「ラスト・タイク-ン」(エリア・カザン監督)の試写の連絡。これは必ず見るつもり。原作、スコット・フィッツジェラルド。脚色は、ハロルド・ピンタ-。キャスティングがすごい。
「文芸」、川村 二郎が、「本居 宣長」について書いている。「新潮」、保田 与重郎、大江 健三郎。おもしろい組み合わせ。久しぶりに保田 与重郎の文章を読む。小林 秀雄に深い畏敬をもっている。その論旨もよくわかるのだが、私としては、承服しがたい部分がある。
「文芸」の、大笹 吉雄の劇評の冒頭、
今、歴史を素材にしたドラマほど、書きにくくなっているものはない。その象徴的な出来ごととして、木下 順二が歴史劇を書かなくなったということがある。なぜそうなったのか。原因はいろいろあるだろうが、もっと、大きいと思われるのは、イデオロギ-としての世界観が崩壊、ないしは相対化したということにある。木下に即してそう思うのは、この劇作家が、精力的に歴史劇の法則とドラマのそれとを一致させようと努力してきた第一人者だからである。
しかし、こういう認識による限り、歴史の法則性に疑いが出れば、歴史劇を書けなくなるのは当然であった。
ところが、同じ号に、木下 順二が「子午線の祀り」を書いているのだから、皮肉というほかはない。ただし、大笹 吉雄の意見はもう少し検討してみる必要がある。
キッシンジャ-が、自分の死後、または25年後まで公開禁止を条件に、アメリカ政府に譲渡した在任中の交信記録が、近い将来に公開される可能性がある。
これは1969年から退任までの8年間、電話の内容をホワイトハウス、国務省の秘書官に速記させ、文書として残したものという。
ニクソン、フォ-ド両大統領ほか、各国首脳の電話、さらに多くの個人的な相手のものまで含まれる。
こういう記録が公表されれば、ヴェトナム戦争、中東戦争の経緯、経過に対する重要な証言が得られるだろう。

1977年12月10日(水)
裕人が風邪の兆候をみせている。
夜になって、百合子が腹痛を訴えて、嘔吐をくりかえした。
私の病状はずっとよくなってきたが、声がかれて、まだいつもの声に戻っていない。
へんな話。
ユ-ゴスラヴィア/チト-大統領夫人、ヨバンカ・ブロズ・チト-が、今年の6月から公式の席に姿を見せない。チト-大統領のソヴィェト・中国・フランス訪問に同行しなかったばかりではなく、軟禁状態におかれていると想像されている。「ヘラルド・トリビュ-ン」は――チト-大統領は座骨神経痛、ヨバンカは糖尿病で、不和という。オ-ストリアの新聞は――ヨバンカがアメリカのCIAに利用されたと見ている。
「ニュ-ズ・ウィ-ク」は――ヨバンカが政府、党の人事問題に口を出して、チト-の不興をかったため、軟禁されたという。
先日のホ-ネッカ-の「問題」とともに、これは注目すべきニュ-スと見る。
ユ-ゴは、チト-独裁の下、安定していると見られているが、複雑な人種問題を抱えている連邦国家で、とくに正教のセルヴィアと、カトリックのクロアチアの対立感情がつよい。
ヨバンカ夫人は、セルヴィア出身なので、人種対立がからんでいるかも知れない。いずれにせよ、共産圏諸国のタガが緩んできているのは間違いない。

1977年12月11日(木)
昨日から、庭師が入って、池を掘りはじめた。
木を植え返したり、地中に埋めてある電気のパイプを掘り起こしたり、わが家としては、かなり大きな工事になる。
池はルネサンスふうの池にしよう、などと勝手なことをホザいているのだが、庭にレンガを敷いて、部屋からすぐに池に出られる。トリもくるだろうし、サカナも飼えるだろう。
大阪の船堂君、来訪。
モンブラン、キリマンジャロなどに登った山男なので、安東 由利子、工藤 淳子、石井 秀明たちを招いて紹介する。
みんなで、「金閣」で食事。
船堂君の話は、おもしろかった。
高度、4000メ-トルで、思考がおかしくなる、とか。ケニアのホテルのショ-は、日本円で40円程度だそうな。
夜、「恋の旅路」(ジョ-ジ・キュ-カ-監督)を見た。これは、TV用の映画。ロ-レンス・オリヴィエ、キャサリン・ヘップバ-ン主演。劇場では公開されなかった。
1911年の設定。有名な弁護士のもとに、富裕な未亡人が依頼する。彼女の莫大な遺産目当てで言い寄った男と婚約したが、途中で、相手の目的が財産目当てと知って、婚約を破棄する。そのため、相手の男から婚約不履行で、逆に訴えられる。このままでは、裁判に勝てる公算はない。
じつは、この弁護士は、40年前に、カナダのトロントで彼女と会っている。当時、彼女は舞台女優。「ヴェニスの商人」の「ポ-シャ」で、ある劇団の巡業でトロントの舞台に立っていた。彼は、舞台を見て彼女に熱をあげ、彼女を口説いた。未亡人のほうは、40年も昔の旅先のロマンスなど、すっかり忘れている。
裁判がはじまる。
相手側の弁護士も有能で――この事件は、未亡人が男に熱をあげたこと、男のほうも未亡人の美貌に心をうばわれたことを立証しようとする。
一方、名弁護士のほうは――未亡人が高齢で、男に口説かれたために一時の気の迷いで、ついつい男にほだされた、と反論する。ところが、未亡人は高齢といわれたため激怒して、自分の弁護士に食ってかかり、退廷させられてしまう。そのあと、名弁護士は、陪審員たちに向かって、切々と愛の意味を説き、みんなを感動させ、不利な状況を逆転させて、みごとに勝訴する。
さて、退廷させられた未亡人のほうは、何もかも計算しての行動だったと明かす。40年前、弁護士をめざしていた若者を愛していたことを明かして、これからは、もう一度、人生をやり直そうと誓って、ふたりで腕を組んで法廷を出て行く。
スト-リ-だけを要約すると、なんともご都合主義めいた法廷ものなので、面白くも何ともないが、ロ-レンス・オリヴィエ、キャサリン・ヘップバ-ンの芝居で、イギリスの風俗劇のおもしろさを堪能できた。
お互いに、初老に達した名優、名女優のやりとりのみごとさ、ドラマの展開の緊張が、コメディ-らしい二人の「関係」(シチュエ-ション)のおかしさ、男女が愛することの「かなしさ」にまで重なってくる。
私たちの劇場では、ほとんど見ることのないコメディだった。

1977年12月13日(土)
11時半、水道橋。
「南窓社」から、「共同通信」の戸部君に連絡する。
昼、上野に出る。「イタリア・ルネサンス装飾展」を見た。メトロポリタン美術館所蔵のもの、ロバ-ト・レ-マン・コレクション。特別めずらしいものはなかった。ただ、ヴェネツィアの、水入れというか瓶は美しい。
メダイヨンの中に、シャルル8世、フェデリ-コ・ダ・モンテフェルトロの像をきざんだものがあったので、心の中で挨拶しておいた。
今日は、あまりツイていない。
「ヘラルド」に行ったが、ひどく混んでいるので、試写はあきらめた。
神田に出て、本を3冊。1冊は、よくわからない本。クレビヨン・フィスの資料(だと思う)。
「あくね」に行ったが、ここも混んでいる。
「弓月」に移った。小川には会えず。オバサンが、丸谷 才一の話をした。7歳頃の丸谷 才一をよくおぼえていた。

1977年12月15日(月)
昨日は、「共同通信」の戸部君に原稿をわたした。「日経」の秋吉さんから督促。
「ドミノ・タ-ゲット」(スタンリ-・クレイマ-監督)を見た。
ジ-ン・ハックマン、キャンディス・バ-ゲン、リチャ-ド・ウィドマ-ク。
愛する女、「エリ-」(キャンディス・バ-ゲン)の夫を殺したため、服役中の「ロイ」(ジ-ン・ハックマン)は、同囚の「マ-ヴィン」(リチャ-ド・ウィドマ-ク)から脱獄に協力しろといわれる。脱獄に成功した彼は、アメリカを脱出して、コスタリカで「エリ-」と再会するが、じつは脱獄をエサにした、国家的な要人の暗殺計画の実行犯に仕立てられていることに気がつく。
めずらしく、ミッキ-・ル-ニ-が出ていた。ぶくぶくに肥っている。これが、あの「アンデイ・ハ-デイ」のなれの果てなのか。
CICに行く。「ラスト・タイク-ン」(エリア・カザン監督)。原作、スコット・フィッツジェラルド。脚色は、ハロルド・ピンタ-。
30年代のハリウッド。若手の敏腕プロデュ-サ-、「モンロ-」(ロバ-ト・デニ-ロ)は、若いイギリス人女性(イングリッド・ボ-ルディンク)に亡き妻の面影を見て、恋に落ちる。これを知った撮影所長は、「モンロ-」の独走をきらって、かれをしりぞける。
キャスティングがすごい。トニ-・カ-ティス、ロバ-ト・ミッチャム、ジャック・ニコルソン。これに、ジャンヌ・モロ-、アンジェリカ・ヒュ-ストン。
エリア・カザンのような演出家でも、どうしようもない衰えを見せている。おなじように、ノスタルジックな気分を描いても、「華麗なるギャッビ-」(ジャック・クレイトン監督)や「イナゴの日」(ジョン・シュレジンジャ-監督)のような作品がある。ところが、カザンはそれぞれのシ-ンを丹念に演出しているだけで、全体にテンポが緩んでいる。テンポが遅ければノスタルジックな気分が出せるわけではない。
5時半、「ジュノン」、松崎 康憲君のインタヴュ-。これは、まあ、うまくいったと思う。「日経」、秋吉君に原稿をわたした。ところが、「映画ファン」の萩谷君に原稿をわたす約束だったことを思い出した。萩谷君に、わるいことをした。
6時半、「山ノ上」で「マリア」に会う。ここにくる途中、安東 由利子、石井 秀明に会ったという。二人とも、「マリア」が私に会うために急いでいると知って、同行しなかったらしい。

1977年12月16日(火)
「山の上」で、萩谷君の原稿を書いた。「マリア」が私についていてくれたのだった。
六本木に。アヌイの「アンチゴ-ヌ」を見に行く。知らない劇団のスタジオ公演。
吉祥寺で、これも知らない劇団のスタジオ公演。ハロルド・ピンタ-の「ダムウェイタ-」をやっているのだが、遠いので敬遠した。
夜、「マンハッタン物語」(ロバ-ト・マリガン監督)を見た。
しがない楽士、「ロッキ-」(スティ-ヴ・マックィ-ン)は、避暑地で知りあった少女、「アンジ-」(ナタリ-・ウッド)と一夜を過ごす。そのため、少女は妊娠する。彼女の愛に胸をうたれた「ロッキ-」は結婚を考える。
夜、雨になった。震度・2程度の微震があった。

1977年12月17日(火)
ひどく暖かい日。9月下旬の気温という。昨日の雨はあがった。
師走というと、ベ-ト-ヴェンの「第九」が出てくる。「フジテレビ」のドラマは、第1次大戦で、捕虜になったドイツ軍の兵士たちが、捕虜収容所で、「第九」を演奏した実話を描いている。最後に、150人のアマチュア演奏家が「第九」の演奏を流したのは驚きだった。

1977年12月18日(水)
一日じゅう、ただ、考えている。
船堂君から手紙。
「キリマンジャロの豹」こと、中田先生、この前は、中国料理をずいぶんたらふくとたべさせていただき、ありがとうございました。先生が「山屋」として精力的にやっておられる話を聞かせてもらって、少し驚いています。ルネサンスふう庭園、とかいう池、なかなか面白そうなことをよくやられますねえ。エマニエルと沖田 総司みたいなですかねえ。でも一番びっくりしたのは、黒い鉄門です。あれで、すぐに先生の家だとわかりました。あのように思い切った門を取り付けるのは、気分がいいでしょうねえ。ほくも、いつかいえでも作るような事があったら、ああいうような門をつけてみたいと思います。
いろいろなあだ名をつけられたことがあるが、「キリマンジャロの豹」というのは、気に入った。
百合子にこの手紙を読ませたが、「エマニエルと沖田 総司」は、わからなかったらしい。「異聞沖田総司」の登場人物なのだが。
門は、私がデザインした。「共同通信」の戸部君も、この門をみて驚いたひとり。しきりに感に耐えないという顔をしていた。それはそうだろう。鉄板を切って作った女のヌ-ドが、そのまま門になっているのだから。私の傑作の一つ。
深夜、北海道の友人、早川 平君に手紙を書く。

1977年12月20日(金)
「ワ-ナ-」、「ワン・オン・ワン」(ラモント・ジョンソン監督)を見た。
バスケットの選手、「ヘンリ-」(ロビ-・ベンソン)は、名門、ウェスタン大にスカウトされるが、小柄で、何につけ、消極的なので、名門校の選手としてやっていけるかどうか悩む。青春映画。
夜、学生たちのコンパに呼ばれている。
安東 つとむが企画したもので、30名が出席。かんたんにいえば忘年会だが、山のメンバ-がほとんど。このほかに、栗原、長谷川 栄二、「双葉社」の沼田 馨君たち。
みんなで、わいわい騒いだり、飲んだり。私は、「マリア」が出席しなかったことが気になっていた。
二次会に行く。まだ大勢が残っている。高円寺のガ-ド下の居酒屋。
終電にやっと間に合った。

1977年12月22日(日)
「公明新聞」に、「私のアメリカン・ブル-ス」の書評。
今年も、映画をたくさん見た。日本映画も見たが、批評を書く機会はなかった。
「幸福の黄色いハンカチ」、「宇宙戦艦ヤマト」、「青春の門・自立編」、「八甲田山」ぐらいか。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()