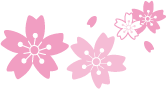1978年6月1日(木)
奇妙な夢をみた。
もともと、あまり夢を見ないのだが、おそらくエロスに関係がある。

1978年6月2日(金)
10時から、翻訳。吉行 淳之介から依頼されたフイリップ・アリンガムを訳した。
吉行 淳之介編、「酒の本」。私は、吉行さんの依頼で、なんとH・L・メンケンも訳している。
H・L・メンケンは、日本で訳されたことがあるのだろうか。戦前の「研究社」、「英語研究」あたりで、対訳のかたちでメンケンが紹介されたり、訳されたことはあったと思われる。しかし、「戦後」、メンケンのエッセイを訳したのは、おそらく私が最初ではないだろうか。
吉行さんは――いささか微醺を帯びたアメリカのご老体が、粋な語り口で、若き日の酔虎伝を語ったものと見て、訳者に私を起用なさったのかも知れない。
禁酒法に対して猛烈に反対しただけに、大酒を食らって、酔いにまかせて原稿を書きとばしていたジャーナリストと見られがちだが――じっさいは、節度をこころえた愛酒家だった。
ビール、ドイツ・ワイン、クラレットが好きだったが、度を過ごして大酒したことのない酒豪だった。
メンケンが若手の新聞記者だった頃、ある日、火事の現場に急行した。消防署勤務の医者が、
――アルコールというやつは、興奮剤じゃなくて、じつは鎮静剤なんだよ。こんな冬
の夜、火事のネタをとっているとき、キュッと一杯やったら、からだが暖まるよ
うな気がする。ところがどっこい、ほんとはサカサマなんだ。
後年、メンケンは書いている。
その医者のことばは、今もなお、心のなかにしみついている。だから、私は夜に
しか、アルコールを口にしない。私の才能をふるい立たせるためではなく、仕事
を終えたあとの昂奮を静めるために。長年にわたって、私はグラス一杯のビール
をあおって原稿を書いたことなどまったくない。私の文章は、高尚な紳士淑女の
みなさんがたには、酔いどれの書いたものに見えるかも知れないが、どうしてど
うして、ウィリアム・ディーン・ハウェルズよろしく、まるっきりシラフ、いと
もおごそかに書いたものである。
ウィリアム・ディーン・ハウェルズは、1837~1920年 偉い作家、批評家だったが、私たちにとってはメンケン以上に遠い存在になってしまった。たいていのもの書きは、死んでしまえばすぐに忘れられるから仕方がないが。
それにしても、吉行さんに頼まれたH・L・メンケンは私にとっては手ごわい相手だった。うまく訳せなかったのは、残念だったが。

1978年6月3日(土)
「伊勢丹」、「ドラン展」。
私はドランにあまり関心がない。ピカソ、マティス、ブラックなどと比較した場合、なぜか魅力が感じられない。ただし、あまり注目されないが、ドランのヌードに、すばらしいものがある。千葉の「川村美術館」で、そんなドランの1枚を見て、私は魂を奪われたような思いがした。このヌードのドランはまさに天才と呼ぶにふさわしいきらめきを見せていた。これに比肩するものは、上野で見た、エゴン・シーレの1枚、パリで見たモジリアーニの1枚だけだった。これに較べれば、やや劣るのだが、ヴァン・ドンゲンの1枚。
今回の「ドラン展」では、「二人の女」を見ることができた。この絵を見て、私はドランのことだけでなく、女のエロスについて考えはじめていた。
片手を頭の上にかざして立つ女。その前に身をかがめ、その女の下腹部に両手をあてて、しなだれかかるもうひとりの女。二人の女は、おそらくレズビエンヌだろう。
この絵には、ドランがやむを得ず隠していた、何か秘密めいたものがあるように思われた。
まるっきりの妄想だが、この二人の女のポージングは、レオナルド・ダヴィンチの「聖アンナ母子」のポーズを逆にしたような気がする。(ただし、幼児のイエスは消してあるとして)。
この次は、「ローランサン展」をやるらしい。これも、ぜひ見るつもり。
「山ノ上」で、「講談社」、徳島 高義、清水 孝一さん。徳島さんに原稿をわたす。しばらく雑談。吉行 淳之介のこと。
「世界文化社」、井上 博君に原稿。待たせてしまった。
6時20分、Y.Kを待っていたところに、吉沢君がきた。3人で「グランプリ」を見た。ノルウェイの人形アニメーション。原題、「The Punch Clufe GRAND PRIX」。(これは、ブロマイドに書いてあった通りに写したので、スペルは間違っているかも知れない)。ストーリーは単純だが、子どもの心理をよくとらえている。日本でも人形アニメは作られはじめたが、不必要にさわがしかったし、ジケッと感傷的だったりする。このノルウェイ人形アニメは、さわやかにユーモラスで、人形の動きに無理がない。見ておいてよかった。
吉沢君が、神田駅の近くの小料理の店に案内してくれた。
Y.K.と。

1978年6月4日(日)
今頃になってバークリーから送ったスプラッターが届いた。船便なので、手荒に扱われたのか、壊れていた。通関量が100円。税関の検査で壊れたのか。これでは使いものにならないが、タネだけは無事だった。
百合子と散歩。プランター、腐葉土を買ってきた。
エリカが送ってほしいというので、百合子といっしょに浴衣を選んでやる。
私は、浴衣を着た夏の女を見ると胸がときめく。
今の若い女の子が身につけている、薄くてさっぱりしたシュミーズ・ドレスも、むき出しのセクシーさより、ぐッとくるエロティシズムを感じさせるが、浴衣は江戸の女たちが自然に身につけたエロティシズムの極致だと思う。
「スケスケの服がはやっているので、下着のおしゃれも大切ね」と、女たちはいう。
しかし、浴衣は透けるから下着をつけなければいけない、という考えかたとは無縁だろう。昔の女が美しかったのは、お腰一枚で、くりっとしたヒップ・ラインを見せたからだろう。
ノーブラという考えかたも、ほんらい浴衣には必要がない。女の乳房はある程度大きくなければならない、という男の論理が、こういう考えかたのうしろ側にある。ペチャパイだろうと、Gサイズだろうと、女の胸もとの美しさを見せることができるのは浴衣だけといっていい。

1978年6月5日(月)
4時、やっと原稿を書く。すぐに仕度して、「山ノ上」に。
「世界文化社」、井上君にわたす。
6時半、神保町からタクシーで新宿に。「コンボイ」(サム・ペキンパー監督)の試写。
トレイラー・トラックのドライヴァー、「ラバー」(クリス・クリストファーソン)は保安官、「ライル」(アーネスト・ボーグナイン)に睨まれている。たまたま、警察のおとり捜査にひっかかり、「ライル」に罰金をとられるが、トラックで逃走する。ドライヴァー仲間に無線で呼びかけ、州内からぞくぞくとトラックが集結する。「コンボイ」は、ほんらい護送船団の意味だが、「トラック野郎」といった含みになる。
警察側とトラック軍団のカー・チェイスは迫力があるが、「ガルシアの首」や「わらの犬」などに比較すべくもない空虚な大作。
私は、サム・ペキンパーのすさまじい暴力描写や、極度に緊張したシーンにスロー・モーションを使う演出や、暴力描写とコントラストをなす悲哀にみちた詩情といったものが好きなのだが、「コンボイ」には、そんなものはなかった。

1978年6月6日(火)
朝からいろいろと電話。
12時半、千葉駅に急いだ。駅の裏に当たる中村酒店の前に出たとき、特急が入ってきた。これに乗らなければ「山ノ上」で会う約束に間に合わない。
それでも、足を早めて駅に向かった。乗れそうもないのだが。
プラットフォームに出たとき、意外なことに、この特急が7番線にいた。私は走った。開いたドアから飛び乗ったとたん、ドアが閉まった。
ラッキーだなあ。
空いている席に腰をおろした。すぐに、背後から車内検札の車掌がきた。特急券、1000円。
車掌が前の席に移動した。3列ほど前の席に外国人がすわっていた。車掌が寄って行って話しかけた。通じない。車掌が困った顔で何か説明する。まったく通じない。しばらく押し問答がつづいた。中年、赤ら顔に口ひげのラテン系の外人だった。その外人も自分の身に何かよからぬことが起こったらしい、と困った顔で、車掌を睨みつけていた。
――手つだってあげようか。
私は車掌に声をかけた。車掌は、ほっとした顔になった。
――できますか。
何ができますか、なのか。車掌は、「英語ができますか」といったのではなく、私が通訳を買って出たので、「お願いできますか」というつもりで、こういったらしい。
私は、この列車が「特急」なので、きみは別に運賃を払う必要がある、と英語でいった。相手は、英語がわからないという。イタリア語ならできるという。
イタリア語で説明した。なんとか通じたらしい。ただ、どうして特急券を買わされるのか、納得できないようすだった。
アルゼンチン人という。
車掌が、私のところにきて、礼をいった。
――どこの国の人ですか。
――アルゼンチンの人。イタリア語しかできないそうです。
東京駅についたとき、私はアルゼンチン人といっしょに5~6番線に出た。浜松町に行くというので、少し話をした。時間があったら、もう少し話をしたかったが、私は、すぐ次の駅で下りなければならなかった。
「ジャーマン・ベーカリー」で、「二見書房」の長谷川君に会う。いっしょに「20世紀フォックス」に行く。「結婚しない女」(ポール・マザースキー監督)の試写。
「エリカ」(ジル・クレイバーグ)は「マーティン」(マイケル・マーフイー)と結婚して16年目。夫が浮気をしたため、勤務先の画家、「ソウル」(アラン・ベイツ)と不倫な関係に入る。ところが「マーティン」は、浮気相手(リサ・ゴーマン)と別れたといって、「エリカ」に復縁をせまる。「エリカ」はこれを拒否して、「結婚しない女」として生きてゆく決心をする。
この原作は、杉崎 和子女史が訳して「二見」から出している。杉崎さんとしては、あまり気ののらない仕事だったらしいが、それでも、ケート・ショパンよりは読まれるだろう。これをきっかけに、存分にいい仕事をなさいますように。
「山ノ上」。長谷川君と別れて、すぐに、「サンリオ」の佐藤君と、若い編集者(名前失念)と会う。このとき、「二見」がアナイス・ニンの「デルタ・オヴ・ヴィーナス」をとったという。「サンリオ」の佐藤君から聞いた。
誰の訳で? 青木 日出夫という。やっぱり、そうか。
アナイスの遺作、「デルタ・オヴ・ヴィーナス」は、ポールの依頼で、私と杉崎さんが「実業之日本」に出版を交渉した。ずいぶん努力したつもりだったが、アナイスのエージェント、ガンサー・スタールマンが、あらたに「ユニ・エージェンシー」と交渉することになった。このとき、青木 日出夫が出てきた。青木君は「ユニ」の幹部だから、「デルタ」の出版権の獲得に動くのは当然だが、交渉の途中で、自分としては「デルタ」を訳す意向はない、と私たちに明言したのだった。
ところが、「二見」にアナイスを売り込んだとき、「デルタ」の翻訳も自分でやることにしたのだろう。
私と杉崎さんは、アナイスの「日記」の出版が目的だったので、「デルタ」は、そのカードだったが、「二見」が「日記」を出版するとは考えられない。
長谷川君は、当然、この経緯を知っていたが、私には伏せておいたのだろう。
青木君が交渉すると知ったとき、結果がこうなると予想していたので、それほどショックはなかったが、これで「日記」はどこでも出せないのが残念だった。
「講談社」、徳島 高義さんに原稿をわたす。吉行 淳之介、井伏 鱒二のこと。
「山ノ上」で、杉崎女史に会う。
「鶴八」に行く。今夜は、私なりの送別会のつもり。
杉崎さんは、アメリカには1年契約で行くことになる。桜美林大学はやめるらしい。惜しいなあ。9年間も在籍したのに。

1978年6月9日(金)
「ワーナー」で、「グッバイ・ガール」(ハーバート・ロス監督)を見るつもりだったが、二日酔い。
百合子が起こしてくれたときは、2時半。
4時半、「ジャーマン・ベーカリー」で、「ほんやく」の若い女性編集者に会う。
「山ノ上」。Y.K.とデート。

1978年6月10日(土)
平賀 源内・輪講。

1978年6月11日(月)
何時も試写ばかり見ているので、劇場で映画を見ることがなくなってしまった。たまには、身銭を切って、映画館に足を運んで、普通の観客として映画を見ることも必要だろう。
「スバル座」で、「ザ・ビートルズ/グレイテスト・ストーリー」をやっている。私は「ビートルズ」ゼネレーションではないが、ハンター・ディヴィスの評伝を訳したことがある。小笠原 豊樹と共訳したのだが、このおかげで、いわば人間としての「ビートルズ」を知ることになった。
「日劇文化」で、ベルイマンの「沈黙」をやっている。これも、じつは見逃している。
「テアトル銀座」で、「太陽がいっぱい」と「カサブランカ」の2本立て。これが最後のロードショー。
「岩波ホール」で、エジプト映画、「ナイルのほとりの物語」。(フセイン・カマール監督)。これは高野 悦子さんが、現地で見て、日本での公開をきめたらしい。高野さんの選んだものなら、まず間違いはないだろう。
新作なら、「白き氷河の果てに」かな。カラコルム、K2登攀のドキュメント。
どれを見てもいい。というより、どれを選んでも、1週間は幸福に過ごせるだろう。そんなことを考えた。ただし、今日も、「メディチ家」に没頭したから、妄想に終わったのだが。
夜、「テレ朝」、「動く標的」(ジャック・スマイト監督)。
ポール・ニューマン、ジュリー・ハリス。ロス・マクドナルド。
「動く標的」は私の訳ではないが、ロス・マクドナルドは、私がつぎつぎに訳して、ミステリーから足を洗ったあと、小笠原 豊樹がロス・マクドナルドの訳者になった。それが奇縁で、私は小笠原君とハンター・ディヴィスの「ビートルズ」を共訳したのだった。
小笠原君とはその後まったく交渉がなかったが、共訳者に私を選んでくれたことを今でも感謝している。

1978年6月12日(月)
夕方、5時14分、宮城県を中心に大きな地震。
震源、宮城県沖、100キロ、深さ40キロ。マグニチュード、7.5。
各地で、家屋の倒壊、火災、貨車の脱線、停電、電話網の麻痺が起きている。宮城県では、仙台を中心に、死者、負傷者が多数。死者、22名。行方不明、1。各地の負傷者、365。
千葉でも、震度4。
新幹線、東北線、首都圏の国電などが、一時ストップした。成田空港も、地震の影響で13分間閉鎖された。
1964年(昭和39年)の新潟地震と同程度の大地震という。
私は、両親が関東大震災を経験しているので、地震には敏感になった。震度3程度の地震でも、昌夫も宇免も、すぐに戸や窓を開け、避難の用意をする。震度4の地震の場合は、裸足で外に飛び出したこともある。
近所の人たちが、そんな二人を笑っていたが、昌夫も宇免も、
「地震のおそろしさを知らないからだ」
といっていた。
私も、妹の純子も、地震に恐怖を感じるようになった。

1978年6月13日(火)
中国の文人、郭 沫若が亡くなった。
12時半、「ジャーマン・ベーカリー」で、「二見」の長谷川君に会う。
「二見」が「デルタ・オヴ・ヴィーナス」をとったことは口にださなかった。長谷川君が口外しない以上、私から言及すべきではない。
「ワーナー」で、「グッバイ・ガール」(ハーバート・ロス監督)を見た。
原作は、ニール・サイモン。去年、結婚していた女優、マーシャ・メイスンのために書いた芝居。いつも男にグッバイされてばかりの「ポーラ」(マーシャ・メイスン)には、10歳の娘、「ルーシー」(クィン・カミングス)がいる。帰宅すると、「ボーイフレンド」から別れの手紙がとどく。そこに、ルーム・シェアしたからといって、失業中の役者、「エリオット」(リチャード・ドレイファス)がころがり込む。
マーシャ・メイスンは、いい女優だと思う。
試写室で、どこかで会った女性編集者を見かけた。村永 大和君の出版記念会で会った「短歌研究」の編集者だった。歩きながら話をした。私とは、ミリューが違うので二度と会うことはないだろう。ちょっと、残念な気がした。
「山ノ上」で、「集英社」の新福君に会う。校正を直す。たまたま、永田君がいっしょにきた。永田君にこれ以上迷惑をかけるわけにいかない。「メデイチ家」は、この夏に完成させると約束した。
果たして、自分でも完成できるかどうかわからない。しかし、約束した以上、実現しないわけにはいかない。なにしろ、大作なので、これを書いているあいだ、雑文が書けない。当然、収入が激減する。映画評はつづけるが、たぶん週1本というペースになる。
夜、「日経」小ホールで、ソヴィエト映画、「ドン・キホーテ」(グレゴリー・コージンツェフ監督)をやる。
私は、シャリアピンの「ドン・キホーテ」G・W・パプスト監督)を見ているので、この「ドン・キホーテ」も見たかった。場所も「日経」なので、吉沢君に頼めば、入れてもらえるだろう。
シャリアピンの「ドン・キホーテ」は、私にとっては、貴重な作品だった。まず、シャリアピン最初にして最後の出演作品だったから。パプストもシャリアピンも、この映画を撮ったあと、すぐに亡命している。さて、つぎに、新人、ミレイユ・バランが「ドルシネア」に起用されたこと。私は、周回遅れのミレイユ・ファンだった。
だが、私は試写を断念した。
講義のあと、安東夫妻、鈴木 和子、石井、中村たちと、「平和亭」に行く。
今年の夏、できれば、ガラン谷をめざしたい。しかし、この谷は、きわめて危険な登山になるので、途中でべース・キャンプを張るかも知れないと話す。

1978年6月14日(水)
朝、松山 俊太郎さんに電話。しばらくぶりだった。
「日経・ショッピング」、鈴木さん、インタヴュー。
「双葉社」、北原 清君、「小説推理」に移ったという。吉田 新一君は、「週刊大衆」編集長に。このところ、「週刊大衆」の落ち込みはひどい。記事に新味がなかった。「アサヒ芸能」と似たような状態なので、大幅な人事異動ということになったらしい。

1978年6月15日(木)
「メディチ家」。
「日経」、吉沢君から電話。「春秋社」の佐藤君に、私の連載の話をしてくれたらしい。吉沢君は、私が大作にとりかかっていることを知っているし、すくなくとも、1年は収入が激減すると見ているのだろう。私の作家生活が不安定なので、こういう仕事を探してくれた。感謝。
吉沢君の電話のあと、すぐに「春秋社」の佐藤君から電話。明日、「山ノ上」で会うことにする。
「三笠書房」の三谷 喜三夫君から電話。「オーメン」続編の件。これは、ことわったほうがいいのだが、三谷君にはいろいろと恩義があるのでことわれなかった。
「三笠書房」の「秘戯」は、5刷。
「オーメン」(リチャード・ドナー監督/1976年)はヒットした。脚色はデヴィッド・セルツァー。主演、グレゴリー・ペック、リー・レミック。76年10月、公開。
すぐに続編が作られた。「オーメン2 ダミアン」は、ドン・テイラー監督/脚色はおなじデヴィッド・セルツァー。ウィリアム・ホールデン、リー・グラント。78年 2月、公開。(81年に、第3作、91年に、TV映画が作られて、日本では劇場公開された。さらに、2006年に、第1作がリメイクされたが、出演者が新人だったこともあって、失敗している。 後記)
4時、「二見」の長谷川君に会う。

1978年6月16日(金)
朝から原稿を書きつづける。スピード・アップする。
夏日になった。
3時から、「フェイク」の試写があるのだが、疲れているので、残念だが予定を変更。百合子が、いろいろ仕度をととのえてくれた。
東京駅。雑踏のなかで、本多 秋五さんを見かけた。挨拶したかったが、そろそろラッシュアワーなので、遠慮する。それに、本多さんが、明治に行くことはわかっていた。
お茶の水。改札を出たところで、声をかける。
本多さんは、なつかしそうに、私の挨拶に応えてくれた。
近くの「ジロー」に寄ろう、という。めずらしいことだった。
本多 秋五 八高で、平野 謙、藤枝 静男を知る。東大国文科、卒。プロレタリア科学研究所に入り。山室 静を知る。
トルストイの「戦争と平和」に没頭して、戦後、1947年、「「戦争と平和」論」を出した。
私は、戦後の「近代文学」から出発したが、この時期、本多 秋五さんととくに親しかったわけではない。本多さんも、とくに私に注目していたわけではない。げんに、「物語 戦後文学史」(1958年~63年)に私は登場していない。私は、本多さんのお人柄に深い敬意をはらっていたが、文学的には、無縁といってよかった。ただし、平野さんが明治の文学部に本多さんを招いたので、そのつながりで本多さんに親しみを感じていた。
いろいろな話題が出た。といっても、戦後の一時期の「近代文学」の思い出にかかわるとりとめのないはなしばかりだったが。
「ジロー」を出て、明治の前まで、話は尽きなかった。吉郎坂で別れた。ここから、「山ノ上」まで、歩いて1分の距離であった。
「集英社」文庫の編集者に、「あとがき」をわたした。
「春秋社」の佐藤 憲一君、初対面だが、すぐにうちとけた。連載は7月から。1回は、12枚程度。それでも、毎月、収入が保証されるようなものだから、ありがたい。
「双葉社」の北原 清君。これも久しぶりだった。私の担当で、散々迷惑をかけた編集者のひとり。久しぶりだったので、話がはずんだ。
「双葉社」は、堤 任君が、労務担当主任になったという。吉田 新一君が「週刊大衆」に移った。その他、かなり大規模な人事異動が行われたらしい。
私は、「週刊大衆」に長編を書いたとき、まったくやる気のない編集者が担当したため、こちらも書く気が起きなかったことを話した。仕事は最小限、そのくせ会社の福祉施設を利用してテニスばかりしている編集者だった。

1978年6月18日(日)
朝、5時、百合子に起こされた。いつもなら、自分で起きるのだが、昨日いっぱい、「メディチ家」にかかっていたので、5時に起きられるかどうか自信がなかった。
百合子は、私を起こして、また眠ってしまった。
今日は、安東たちが参加しないので、ボンベ、コッヘルを用意した。
7時半、新宿。吉沢君の姿が見えない。今日はひとりか。8時16分発の電車に乗った。吉沢君が乗ってきたが、私に気がつかない。ザックを置いて、プラットフォームに出た。私を探しているらしい。私は車内で、席を変えて、吉沢君のザックを棚にのせてやった。
発車1分前に、吉沢君が戻ってきた。私がこないので、ザックをとりにもどったらしい。私を見て安心したようだった。
お互いに、笑顔になる。
9時半から歩きだしたが、暑くなってきた。これは、マズったか。
頂上に出る峠で小休止すべきだったのに、吉沢君が、
――(このまま)行きますか?
と訊いたので、うなづいてしまった。
どうも、いつもと違うような気がする。
高気圧が、張り出してきたのか。暑さが、私たちの行動に影響している。こういう日の山行は注意しなければいけない。
関東はカラ梅雨で、この山も晴れ、時々曇り、と判断した。しかし、蒸し暑い。
峠から頂上までがキツかった。私は、3度も足をとめた。吉沢君も、ふらつきながら歩いている。
2時、頂上。
見ると、吉沢君が蒼白になっている。熱射病の初期。すぐに水を飲ませる。日蔭にマットを敷いて寝かせた。タオルに水をかけて、首のまわりに巻き付けてやった。
――少し、寝ていたほうがいい。
私も、新聞紙をひろげて横になった。そのまま寝込んでしまった。
眼がさめたのは、4時。
この暑さのなか、じっと立ちつくしていることも耐えがたい。すぐに、ティーを沸かして、角砂糖を放り込み、吉沢君に飲ませた。
――下りよう。
やがて、夕日が落ちて行く。太陽の沈む光景は厳粛で、まるで何かの儀式のようで、私たちの山行の終わりが、こうした荘厳さでしめくくられることに、私は挫折感をおぼえた。吉沢君もおなじことを感じていたようだった。
こんな山行ははじめてだった。とにかくバテた。
(あとで知ったのだが、福島の市民マラソンに参加したランナーが、四十数名も倒れ、17名が病院にかつぎ込まれた。20日、朝、青年2人が死亡。太平洋高気圧が日本からアメリカまで張り出して、その強さは16年ぶりという。猛暑。東京は、31.6度)
いつかまた、このコースを歩いてやる。こんどは失敗しないからな。
麓でラーメンをすすりながら、心に誓った。

1978年6月21日(水)
「メディチ家」。少しづつ、自信をもって書き進めている。
「週刊サンケイ」長岡さん。「日経」、吉沢君。原稿の依頼。
4時、中村君に、「夕刊フジ」の書評を届けてもらう。
この日、風が強い。台風の影響出、総武線にまた架線事故があったらしい。
ひと抱えのバラを わたくしのために買う
イラストレーターのやまぐち・はるみの句。何かで目についた。
やまぐち・はるみは、「パルコ」、「マンズ・ワイン」、森 英恵のランジェリーのアド・イラストレーションで知られている。この俳句は月並みだが、月並みだっていい。
1978年6月22日(木)
暑い。台風は、熱帯性低気圧に変化した。
暑いので、夕方、出かけることにする。
俳句じゃないからね。イヒヒヒ。
昨日、尾上 多賀之丞が亡くなった。人間国宝、90歳。明治20年生まれ。
母の宇免は、多賀之丞もよく見ていたが、私はあまり見ていない。つまり、菊五郎(六代目)を見ていないということになる。それでも、「盛綱」や「三婆」の多賀之丞は見ている。
明治、大正、昭和、三代を女形で通した。何しろ芸歴が長い。初舞台から、相手をつとめたことがなかったのは、団十郎(九代目)、菊五郎(五代目)、左団次(初代)の三人だけというから、すごい。
私は、ずいぶん前に多賀之丞を見た。で、どうだったか。
うまい役者かどうか、どこがうまいのかわからなかった。
8時、「山ノ上」。「二見」の長谷川君に会う。
吉沢君がきた。先日の山行。お互いに失敗を笑いあう。しばらくして、船坂 裕君。
みんなで「あくね」に行く。
9時半、松山 俊太郎さんがきた。
松山さんと会うのはじつに久しぶりだが、相変わらず怪気炎をあげていた。
横溝 正史が「メディチ家犯罪史」という本を書いているという。驚いた。ぜひ、拝借したい、と申し入れる。

1978年6月23日(金)
日活映画、「恋の狩人」、「牝猫の匂い」、「愛のぬくもり」、「女高生芸者」の4本がワイセツに当たるとして、製作責任者、監督6人と映倫審査員3人が幇助罪に問われた事件の判決が、東京地裁で開かれ、全員、無罪になった。
この裁判は、警察権力の不当な干渉としての性格を強く帯びていた。この判決では、「性行為などを直接描写するのではなく、本件のようにそれを連想させるだけの場面がワイセツに当たるかどうかの判断は、原則として映倫審査の判断を尋ねるべき」とする。これは当然だが、「性行為など」とあるのは、解釈が拡大されるおそれがある。
現在の検察が、性表現の変化や、一般の性意識の変化について無知であり、不当な弾圧をみせていることは非難されてしかるべきと考える。
D・H・ロレンスの「チャタレー夫人」(伊藤 整訳)をワイセツとした最高裁の判決は、なんと大正7年6月の大審院判決にもとずくものという。こんな判例が、その後も生きづづけ、「悪徳の栄え」、「四畳半襖の下張」、「壇の浦夜合戦記」などの古典をことごとく有罪に追い込んでいる。
先進国がポーノグラフィーの解禁に踏み切り、日本でも、性表現に対する観念、価値観、認識が大きく変化した。にもかかわらず、時代錯誤の判決だけがオバケのように生きのびて、私たちに大きな制約、屈辱感、ひいては表現の自由の侵害をあたえているのは恥としかいえない。
日活映画の性表現などをワイセツとするのはあたらない。すでに先進国で実現しているように、やがてわが国もまた、ポーノグラフィーが全面的に解禁されるだろう、と私は考える。
夜、10時、「テレ朝」で、「紳士は金髪がお好き」(ハワード・ホークス監督)を見た。マリリンの映画は、もう何回も見ている。「ローレライ」(マリリン・モンロー)、「ドロシー」(ジェーン・ラッセル)の歌、踊りは、だいたい頭に入っている。今回は、1928年、パラマウントの映画とどう違うのか、考えてみた。28年のヴァージョンは「ローレライ」(ルース・テイラー)、「ドロシー」が(アリス・ホワイト)。むろん、私は見ていない。今後も、見る可能性は絶無だろう。しかし、1928年ヴァージョンのどういう部分で、ハワード・ホークスがマリリンを「ローレライ」に起用したのか、想像できるのだが。

1978年6月24日(土)
「メディチ家」は、ようやく、4章あたり。
この作品は、どうしても夏の間に「集英社」にわたさなければならない。
ほんとうは、どこかで連載できれば、助かるのだが。私は編集者に知り合いがほとんどいない。しかも、ルネサンスに関心をもつ編集者はまずいないだろう。こういうものを連載させてくれる場所はないものか。
「山ノ上」。「翻訳技術協会」、森井 春樹さん。聞いたことのない組織だが、翻訳者を養成する機関で、12クラスあり、1クラス、30名。私に、半年間、講義をしてほしいという。
翻訳者を養成することはできないわけではない。僣越ながら、中田耕治を講師に招くのはいちおう妥当な人選に違いない。中田耕治さんは、長年、俳優、女優のタマゴを相手にしてきたし、大学でも教えている。いちおう適任にちがいない。
だが、難点が二つある。
半年間、私の講義を聞いても翻訳家になれない。人を育てるということは、はるかに時間がかかる仕事なのだ。
あいにく現在の私はまったく時間的な余裕がない。個人的なことだが――今年はエリカがアメリカから帰ってくる。裕人が進学する。
仕事が重なっている。「メディチ家」の書き下ろしがある。これだけでも眼がくらみそうだが、「サンリオ」、「二見書房」、さらに「三笠書房」の「オーメン 2」と、目白押しに仕事が待っている。
若い頃の中田先生は、いささかエナージェティックだったが、いまや、疲労困バイ、疲怠、ドバの如し。
森井さんにお断わり申しあげたが、それなら、講演でも、という。しばらく考えた。大森で、ルネサンスの講義をしたことを考えれば、ずっと楽だろうと思う。けっきょく、9月2日に講演することで承知した。
中村 継男に頼んで、吉沢君に連絡をとってもらう。
「集英社」、桜木 三郎君。
「少年ジャンプ」の編集者なので、多忙をきわめている。それなのに、私を相手に、長いことつきあってくれた。帰りは、桜木君がハイヤーを呼んでくれた。

1978年6月28日(水)
雨がつづいている。
ひたすら、「メディチ家」にとりかかっている。ルネサンスの名家に生きた女たちの人生など、誰か読んでくれるのだろうか。
私の仕事はずいぶん特殊なものなのだ。私の内面の問題がからみあっているはずなのだから。もっとも、誰も気がつかないかも知れない。
「面白半分」(8月号)で、山本 容朗がこんなことを書いていた。
吉行(淳之介)さんに「夏の休暇」という作品がある。少年が父とその愛人らしい若い女性と火山のある島へ行く話だが、この作家を語る場合はずせない小説の一つだと思う。
ご当人から、この夜聞いたところによると、「この若い女性」は完全なフィクションだという。実際は両親と三宅島へ行ったのだ。同じ題材で、父親や女性の立場から、つまり外側から書いたのが「島へ行く」と「風景の中の関係」の二作品だが、ある評論家は「風景の中の関係」は、彼の少年時の記憶の底にある、父や大人の性にまつわる原風景をえがいている」と評した。「父の若い愛人が作りもの」ということになると、この論評はどうなるのでしょうか。」
この評論家というのは、私のことだろう。しかし、山本 容朗というもの書きの低劣さに驚いた。「父の若い愛人が作りもの」ということになると、この論評はどうなるのでしょうか。」と、揶揄めいたいいかたをしているが、まるで鬼の首でもとったようなどや顔がいやしい。この若い女が作りものであろうとなかろうと、吉行は、三宅島へ行ったことを小説に書くことで、少年の記憶の底にある、父や大人の性をからめて書きたかったのだろう。私が、少年の性にまつわる原風景を描いたと見たことのどこが間違っているのか。
山本 容朗は、文壇のゴシップをあさって生きている虫けらのごときもので、文壇には昔からこの種の寄生虫(パラサイト)が棲息している。
夜、森井 春樹さんから電話。2カ月、講義してもらえないかという。申し訳ないが、お断り申し上げた。ほんとうに時間がないので。
吉沢君に「スター・ウォーズ」の映画評を送る。

1978年6月29日(木)
思いがけない夢。
和田 芳恵さんのこと。「メディチ家」を読んでほしいと思う気もちが、在りし日の和田さんの姿をよみがえらせたのか。
しばらく、茫然としていた。5時過ぎ。
あとで考えたのは――最近出たはかりの和田さんの「雪女」の印象が心に残ったらしいこと。最後の作品、「逢いたいひと」が、「マリア」、「Y.K」のことと重なったのではないか、という気がした。
ビアンカ・ブォナヴェンチェリと、その娘、ペッレリーナ。おもしろくなってきた。
中世の封建社会のように、高度に発達した社会では――ギルドのメンバーは、物質的利益の増大ではなく、伝統的な生活水準を満足させるだけのものを求めて努力した。ルネサンスでは、これは富の獲得と収益になった。そして、過剰な消費があらわれる。

1978年6月30日(金)
晴れ。不快指数が高い。夜明け。
入浴して、もう一度、寝てしまった。起きたのは、8時半。
午前中。「共同通信」、戸部さんから電話。思いがけず、柴田 錬三郎の訃報。追悼文の依頼。午後1時に電話で送る。
柴田 錬三郎 (1917~78年) 慶応大、予科、21歳で、「十円紙幣」を「三田文学」に発表。1940年、支那文学科、卒。戦時中、台湾南方で航海中、撃沈され、奇蹟的に救助された。戦後、「日本読書新聞949年、文筆業に入り、1951年、「イエスの裔(すえ)」で直木賞。その後、「眠狂四郎」のシリーズなどで、空前のベストセラー作家になった。今朝、2時45分、肺性心のため、新宿区信濃町の慶応病院で死去。61歳。
私は、戦後、作家論めいたものをはじめて書いたが、「新小説」で、私を痛罵したのが柴田 錬三郎だった。それ以来、柴田 錬三郎を敬遠してきたが、その後、慶応系の文学者の集まりに顔を出すようになって、いくらか親しくなった。それだけの関係で、追悼文を書くのはどうか、と思ったが、大衆文学の批評家など、どこにもいないので、戸部さんも困ったのではないか。できれば尾崎 秀樹あたりに依頼したかったはずだが、すでにほかの新聞に先を越されて、私に白羽の矢を立てたのだろう。
1時5分、戸部さんに原稿を送った。
とにかく、私は律儀なもの書きなのである。
柴田 錬三郎は、昨年9月、大病をして、一時休筆した。当時、「週刊文春」で、長編、「復讐四十七士」を連載中だった。
何しろ、大流行作家だったから、極度の過労で倒れたらしい。「週刊文春」の長編は中断したが、「読売」の「曲者時代」は大詰めをむかえて、休載できなかった。自分でも病院で書きつづけるつもりで、大きなバッグに資料をつめ込んで都内の病院に入院した。
ところが、入院した直後に、昏睡状態に陥った。連載は1日分だけ余裕があったという。24時間、昏睡状態だったが、柴田 錬三郎は意識を回復した。
翌日から、最終回までの15日分を、作家はベッドで書き続けた。
午前中は、点滴。その効果があらわれる午後から執筆。1回分、書き終わると、ぐったりして寝込む。熱が39度にあがる。また点滴。熱が下がるとまた原稿用紙にペンを走らせる。
こういう悪戦苦闘がつづいて、ついに新聞連載は完結した。
こういう流行作家の生活は、私などの想像を絶しているが、それでも自分の作品を何とか完結させようと必死に書きつづけた柴田 錬三郎には頭がさがる。
入院生活は、ほとんど9か月におよんだが、この6月、退院したと聞いた。
それでも、1カ月後に、白玉楼中の人となった。
午後1時5分、「共同通信」、戸部さんに柴田 錬三郎・追悼を電話で送る。
柴田 錬三郎の逝去に蔽われてしまったが、本多 顕彰(あきら)が亡くなった。英文学者、批評家。享年、79歳。
私はこの批評家に面識がなかった。しかし、本多さんの書くものはよく読んできた。翻訳もすぐれたものが多かった。
いつも、端正な文章で、おだやかに作品の月旦を書いていた。ほかの批評家のように、するどい裁断、分析をこころみるのではなく、批評する側の教養の深さ、判断の基準が、イギリスの批評家のように、重厚ながら、おだやかに迫ってくる。否定的な批評をする場合でも、相手に深傷(ふかで)を負わせないあたりが、本多さんの「芸」だったと思われる。むろん、私などが影響を受けようはずもなかったが。
夜、10時、「TBS」で、「悪魔の追跡」(ジャック・スターレット監督)。
ピーター・フォンダ、ウォーレン・オーツの主演。
「ロジャー」(ピーター・フォンダ)と「フランク」(ウォーレン・オーツ)は、それぞれ妻を同伴して、大型ワゴンで旅行中。偶然、オカルト宗教団体の儀式で行われた殺人を目撃したため、行く先々で危険にさらされる。私の好きな映画。
*作家の日記77~78年 完*