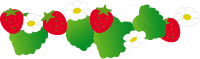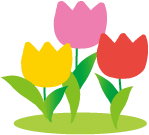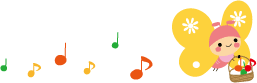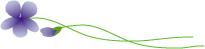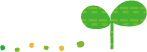2018年元旦。
喪中につき、新年の挨拶は遠慮させていただいた。
2017年3月、妻、中田 百合子の他界という不幸に見舞われたが、その折り、いろいろな方から懇ろなお悔やみを頂いた。ここであらためてお礼を申しあげたい。
その3月から現在までブログを中断したが、これほど長く休載するとは自分でも予想しなかった。
妻の死後、まったく何も書かずただ休筆をつづけた。どこからも原稿の依頼があったわけではないので、私の休筆には何の意味もなかったが、友人に手紙も書かなかったし、ブログさえ書く気が起きなかった。
ブログを書かなくなった理由もない。妻の喪に服して、とか「孤独に耐えて生きて行く」といった、りっぱな信念があったわけではなくて、ただ、何もする気がなく、本を読んだり、若い頃に見た映画を見直したり、そんな日々を過ごしていた。
北鮮の大陸間弾道ミサイルの実験による情勢の緊迫化、トランプによるイスラエルの首都認定による中東情勢の激変、西側の諸国の揺らぎ、中国、ロシアなどの権威主義的な動き、さまざまなテロリズムなど、世界的に混迷が深刻になった時代をよそに、毎日、ただひたすら無為に過ごしていたのだった。
歳末、見る気もなく、テレビを見ていた。
映画は、ラスト前の数カット。
ワン・カット見た瞬間に、ジョン・ヒュ-ストンの「黄金」とわかった。映画のラストで、仲間を裏切って、ロバに黄金の砂嚢を積んで逃亡をはかったハンフリ-・ボガ-トが、悪人の原住民たちに殺される。原住民たちは、市場で盗んだロバを売ろうとするが、盗んだロバと見破られて警察に逮捕される。
ボガ-トを追った仲間ふたり(ウォルタ-・ヒュ-ストン、ティム・ホルト)は、自分たちが苦心して採取した砂金の砂嚢が、無知な原住民に破られて、金がすべて風に散ってしまったことを見届ける。それまでの苦労がすべて無に帰した。
私たちは、ふたりがもはやどうにもならない状況に直面したことに、ひそかな同情めいた感動をおぼえる。
と、つぎの瞬間、ウォルタ-・ヒュ-ストンが、腹をかかえて哄笑する。その笑いはひたすら明るいもので、おかしくておかしくてたまらない、といった笑いだった。ウォルタ-・ヒュ-ストンは何を笑っているのか。その笑いは何を意味しているのか。このふたりもまた、前途にまったく希望はない。笑っていられる状況ではないのだ。若いティム・ホルトには理解できない。ウォルタ-は笑い続ける。
ティム・ホルトはけげんな顔をするが、哄笑するウォルタ-にうながされて、自分も笑いだす。人生の不条理に直面する。そんな絶望的な状況のなかでは、自分のドジを含めて、すべてを笑いとばすしかない瞬間もあるのだ。それまでつづけた採金の作業がまったく意味がなかったことを腹の底から笑いとばそうとする。このとき、観客は、ふたりの笑いに共感する。それはけっして自嘲の笑いではない。人生の不条理に対する笑いなのだ。
ラストは、砂嚢が風に吹かれて、みるみるうちに砂に埋まってゆく。……
わずか数カットのラスト・シ-ンだが、いろいろなことが押し寄せてきた。
そのいろいろなことの中には――映画「黄金」が公開された頃の私が何を考えていたのか、そんなことまでも含まれていた。当時の私は、芝居の演出を手がけはじめていた。芝居の費用をかせぐために、ひたすら小説を書きつづけていた。
「黄金」の原作者、B・トレヴンは、ほとんど無名に近い作家だったが、この映画が作られたせいか、当時の前衛的な出版社、「ニュ-・ダイレクション」から、遺作が数冊、出たことを思い出す。
若い頃の私は、いつか機会があれば、ホレイス・マッコイとB・トレヴンを翻訳しようと思っていた。どうせ大学のアメリカ文学研究者なんか、誰ひとり、こうした作家に目を向けるはずもない。(ホレイス・マッコイは、のちに常盤 新平が訳している。)
映画、「黄金」は、アカデミ-監督賞、脚色賞をうけた。ウォルタ-・ヒュ-ストンは、助演男優賞をうけている。
この少しあと、マッカ-シ-の「赤狩り」が、ハリウッドを襲った。
ジョン・ヒュ-ストンは、ウィリアム・ワイラ-たちと、マッカ-シ-に対抗して「アメリカ憲法修正第一条委員会」を作って抵抗した。
その結果、ハリウッドを離れて、しばらくイギリスで活動した。「アフリカの女王」(51年)で、ボガ-トがアカデミ-主演男優賞をとった。
ジョン・ヒュ-ストン自身が、一流の映画監督だっただけでなく、俳優としても多数の作品に出ている。晩年は、父のウォルタ-・ヒュ-ストンによく似てきた。
娘のアンジェリカも、女優だけでなく監督をつづけている。
私は、テレビ・ミュ-ジカル、「SMASH」(2013)のファンだが、アンジェリカ・ヒュ-ストンがフランス語で歌うシャンソン、「アデュ-・モン・ク-ル」に感動した。(ただし、このシ-ンはテレビでは使われていない。残念ながらカットされた。)
映画、「黄金」のラスト・シ-ンの数カットを見ただけだが、「黄金」のラスト・シ-ンから、アンジェリカ・ヒュ-ストンのシャンソンまで、つぎからつぎに、とりとめもなく、いろいろなことを思い出した。
そして、12月24日。クリスマス。世はなべてこともなし。