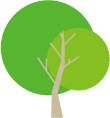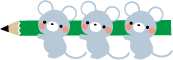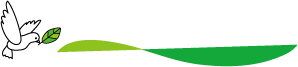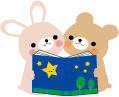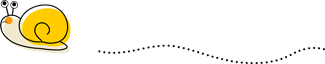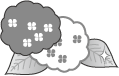1977年5月25日
李文翔夫人から、いつか送った写真の礼状が届く。
文翔氏は4年前に亡くなったという。残念なことをした。英文でお悔やみを送った。
小泉 まさ美が、百合子と渡米の準備の相談にくる。
杉崎 和子女史に電話で、来週・火曜日に会いたいとつたえた。
夜、中村 継男から電話。
久しぶりに音楽を聞きながら、酒を飲む。

1977年5月26日
午後から雨。
「サンケイ」文化部の四方 繁子さんから電話。
原 耕平君、島崎君に電話。「週刊大衆」の堤 任君から電話。安東夫人に電話。
石本君が、画集2冊を届けてくれた。百合子が焼き鳥を出してくれた。石本君といっしょにたべながら話をする。
夜、ヘミングウェイを読む。
1977年5月27日
朝、曇りがちながら、晴れてきた。もともと、雨という予想だった。こういうお天気ならいっそ雨のほうがありがたいのに。土曜日、日曜日にかけて雨が降るのは困る。
朝、6時40分から原稿を書く。
午後2時、「ジャ-マン・ベ-カリ-」で、四方 繁子さんに原稿をわたす。和田 芳恵著、「暗い流れ」の書評。四方さんの話で、三浦 浩さんの病状があまりよくないと知った。三浦 浩さんは、せっかく、作家として登場しながら、思わぬ病気で苦しむことになった。暗然たる思いがある。
島崎君と会っているとき、原 耕平君の部下の女の子が原稿をとりにきた。エッセイ、「ヘミングウェイ」雑記。
今日の試写は、「マイ・ラヴ」(クロ-ド・ルル-シュ監督)。ルル-シュは好きな監督のひとりだが、「愛よ もう一度」にしても、この作品にしても、どこか弛緩した印象がある。
簡単にいえば、「ヌ-ヴェル・バ-グ」がもはやヌ-ヴェル・バ-グでなくなってしまった、ということ。
JRでお茶の水に。駅の前に出たとたんに、鈴木 由子に会った。立ち話をしているところに、工藤 淳子がきた。いずれも登山のメンバ-。
6時半、新宿。駅ビルの8階。杉崎女史と会う。「プチ・モンド」に行ったが、たいへんな混みようで、どの階も、人であふれている。やっと、イタリア料理のリストランテに入った。人ごこちがついたので杉崎女史と話をする。
アナイス・ニンの短編を、「スバル」にもって行くことになった。桜木 三郎が尽力してくれるので、うまく行くかも知れない。
杉崎女史と話しているところに、「日経」の吉沢君、安東 由利子がきた。しばらく雑談。そこに、こんどは「双葉社」の堤 任君、渡辺君がきた。なにしろ金曜日の新宿なので、どこも混雑している。「みちのく」に行こう、ということになった。
ところが、きゅうに杉崎女史が帰ることになった。体調がすぐれないとか。
杉崎女史と別れてすぐに、吉沢君、安東 由利子も帰るという。明日のスケジュ-ルがあるので。
けっきょく、私は堤 任君、渡辺君といっしょに「みちのく」に行く。ここで、大いに飲んだが、私も明日の予定があるので、終電の前に電車に乗った。