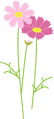1977年9月7日(水)
とにかく、本を読まなければいけない。
もともと、私の読書は、手にした本を再読するかどうかをきめるために読むようなもので、ほとんどの本は、届いて来た日にすぐ目を通すだけで、二度と読まない。
そのかわり、再読すると決めた本は、それからしばらくして、じっくり精読する。 いつかまた読むべき本は、大切にとっておく。いつ読み返すかわからないが、かならず、もう一度読むことにして。
ロココの時代。
売春は、当時の女性にとって日常のアンニュイから逃避するための安易な手段だった、と見ていい。女がさまざまな因習にがんじがらめにされていた時代、さまざまなしきたりや、モラルをかなぐり捨てて、春をひさぐ。これは、時代のモラルに束縛されまいとする女にとって、まさにうってつけの享楽だったに違いない。
ロココにおけるセックスの戯れは、ただ遊ぶための遊びを、無節操に追いもとめ、ついには堕落の一途をたどった。
当時、色豪として知られていたリ-ニュ大公は、堕落したデイボ-シュ(道楽者)だったが、温和な人柄だったらしい。
一方、この時代の高級娼婦(グラン・クルティザ-ヌ)は、お人形よろしく、美々しく着飾った上流夫人の「恋愛」とは対照的に、ひたすら陽気で、気まぐれ、あでやかで、比類のないものだった。たとえば、エロティックで奔放な画風で知られるボ-ドワンの描いたロココの娼婦たちの姿が今につたえられている。
この時代、表現は徹底して自由になり、女たちをとり巻く息吹きも、艶っぽく、挑発的になった。おかげで、一般庶民の女たちまでが、娼婦(クルティザ-ヌ)にひそかな軽蔑のまなざしを向けながら、同時に、好奇心にかられはじめた。
代わりばえのしない日常に倦んでいればこそ、娼婦(クルティザ-ヌ)にあこがれ、あるいは嫉妬したのではないか。
こういう女の歴史は、ギリシャのヘタイラからルネサンスの娼婦につながっている。
ロココの娼婦たちは、厚顔にも、聖職者のとり巻きとして、サロンで、性的な魅力をふりまいていた。
ここから、現代の娼婦たちについて考えてみよう。
![]()
1977年9月10日(土)
20 ロココの女たちは輸出されていた。
ロシア皇帝や、インドのサルタンたちが、フランスの美女を買い求めた。
(価格はいくらだったのか。輸出経路は? 所要日数は? 調べること。)
オペラ・フランセ-ズは、高級娼婦の養成所だった。
娼婦なのだから、彼女を買った男は、「情夫」(アマン)として遇されるが、金の切れ目が縁の切れ目。たおやかな、しかし、非情なモンストルは、おいぼれの守銭奴ばかりか、若い放蕩者からも、遠慮会釈なく黄白をしぼりとる。
ときには、「情夫」(アマン)の正式の妻を追い出して、首尾よく、「妻の座」を奪うものも出てくる。
途方もない贅沢になれきっていた娼婦にしては、ごくささやかな、月々の「お手当て」で満足した高級娼婦もいる。
しかし、この時代、フランス文化の思想と現実を体現していたのは彼女たちだった。
ロココの女たちについて、もう少し調べること。
話はちがうが、ル-マニア国立ブロエシュチ劇場の芝居を見たい。こんな劇団がきていることも知らなかった。
この一行は、「前進座」を見学して、歌舞伎の下座、立ち回りを見学したという。
三味線、鳴りもので、川の流れや雪の降る情景まで出せると知って、
「簡素ななかに、これだけ鋭い表現ができるというのは驚き。日本の伝統演劇の深さに打たれた」
と、団長以下が驚嘆したらしい。(むろん、お世辞半分だろう。)
どういう劇団なのかしらないが――共産圏のル-マニアのことだから、おそらくスタニスラフスキ-を金科玉条にしている劇団だろう、と思う。この劇団の俳優、イオン・ルチアンが、返礼として「ある女の朝」というパントマイムをやって見せたらしい。
朝、目ざめた女が、ベッドを離れて、お化粧をはじめ、外出するまで。
「女形(おやま)の河原崎国太郎さんを前にして、女を演じるのはおこがましいのですが」
といった。
これに対して、国太郎は、
「こちらこそ勉強させていただきました」
と答えたという。
私は、バロ-や、マルセル・マルソ-のマイムを見たり、テアトロ・エスパニョルのエチェガライのマイム、イタリアのエドワルド・フイリッポのマイムも見てきた。しかし、共産圏の役者のパントマイムは見たことがない。もっと早く知っていたら、ティケットを手配したのに。
ル-マニアの女優では、エルヴイ-ル・ポペスコ、ポ-ラ・イルリ-ぐらいしか知らない。残念に思っている。