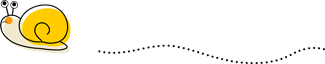竹原 陽子さんは、私と会ってから、私の旧作、「おお 季節よ 城よ」を読んでくださった。私が、自作のなかで、原 民喜についてふれていると知ったからだった。私としては、ただ恐縮するばかりだが、竹原さんはわざわざ古書を探してくださったという。そして入手なさった本に新聞の切り抜きが入っていたという。前の持ち主が、私の本を読んで、たまたま関連する新聞記事を見つけたものらしい。
私は、自作の書評など気にしたこともない。ところが、竹原さんのお手紙を拝見して、少し気になったので、できればコピ-をお送り願えないだろうか、と電話した。
竹原さんはその記事を送ってくださった。
戦中から戦後にかけての、多彩な女性たちとの出会いと別れを赤裸々に回想した自伝的小説である。戦争中、文科の学生だった著者は、勤労動員で埼玉県の農家に手伝いに行き、少女に誘われて初めて女を知り、現実の衝撃に言いようのない不安を覚える。
戦争が終わり、飢えと混乱の中での生活が始まる。貪欲(どんよく)に本を買いあさり、映画やレコ-ドに新しい時代の息吹を吸収する著者。その一方で、行きずりの女、娼婦、女優などとのかかわり、大切なのは欲望であって所有ではない、という人生観がこうした体験から生まれてくる。熱き時代の生がリアルに再現されている。(オ-ル出版・一、五〇〇円)
書評というほどの内容ではない。せいぜい新刊紹介といった記事だが、鉛筆で、日時がメモしてあった。竹原さんは、平成2年11月18日、「日経」の文化面に出たと推測している。
「おお 季節よ 城よ」は、平成2年9月15日/刊行なので、出版されて2か月後に、この新刊紹介が出たことになる。その読者が、たまたまこの記事を切り抜いて、本に挟んでおいたものだろうか。私は、そのことに感動した。私の作品を読んでくれた読者がいる、それはそれでうれしいことだったが、私が感動したのはもう少し違うことの「発見」にあった。
じつに28年後に、著者としての私が読んだこの短い記事は、私にとっては貴重なものになった。
竹原 陽子さんの推測通り、「日経」(平成2年11月18日)の記事なのだが、この記事を書いた記者は、当時、「日経」の文化部にいた吉沢 正英に違いない。
私はこの記事を目にしてしばらくは声を失った。
私は、かなり長期間、「日経」の映画批評を担当していた。私のコラムを担当してくれたのが吉沢 正英君だった。
私のコラムはゆうに100本を越えたはずで、一部では注目されたと思われる。吉沢君と私は、ただの執筆者と編集者という関係から始まったが、やがてお互いに登山に熱中していることがわかって、いっしょに山に登るようになった。
私は、けっこう多忙だった。もの書きとして原稿を書きながら、大学で講義をつづけていた。その間に、映画の試写室を飛びまわったり、芝居小屋通いもあって、毎週、登山をするスケデュ-ルは立てられなかったが、2週間に1度は天候のいかんにかかわらず登山するときめていた。
吉沢君と新宿駅で落ち合う。プラットフォ-ムの立ち話でその日のコ-スを決める。いわゆるカモシカ山行なので、ふつうの登山者に会わないコ-スばかり。いざとなったら、ツェルト頼りにビバ-ク・野宿はもとより覚悟。豪雨・豪雪でも、ひたすら歩く。帰りは、麓のどこかで一杯やるか、鄙びた店で一膳メシにありつく。できれば、鄙びた温泉で汗を流して、夜ふけの田舎道を鉄道の駅まで。
そんな登山をつづけた。やがて、登山のグル-プができたが、いっしょに行きたい希望者がいれば、その人のレベルにあわせて、北アルプス、南アルプスから、秩父、高尾まで。お互いひねくれ者なので有名な山はなるべく避けて、あまり知られていないが、地図に破線もなくて、実際にはけっこうむずかしい山に登ったり。
吉沢君は沢登りが好きで、むずかしい沢を見つけると、自分ひとりの山行で何度も通って、いろいろなヴァリエ-ション・ル-トをたどるのだった。
吉沢 正英は私の親友のひとりになった。
今年の1月24日、群馬県の草津白根山が噴火して、火口に近いスキ-場で、訓練していた陸軍の兵士1人が噴石に当たって死亡した。ほかの隊員7名、スキ-客4名が負傷。ロ-プウェイの山頂駅付近に、一時、80名がとり残され、自衛隊、警察などによって救助された。そんな記事を読んだとき、私はすぐに吉沢君を思い出した。
私は吉沢君といっしょに、夏の草津白根を縦走したことがあったが、ちょうどこの噴火した火口近くでバテた。すっかり疲労して山頂にたどりついた。吉沢君は、あまり疲れたようすも見せなかった。
しばらくして、この山で、火山性の有毒ガスのため、登山者が落命する事故が起きたことを思い出す。
吉沢君の記事を見たとき――なぜか、原 民喜、加藤 道夫、江藤 淳、それぞれ特別な死を選んだ人たちのことを思い出した。さらには山川 方夫、田久保 英夫、桂 芳久たちのことが走馬灯のように頭をかすめた。吉沢君が慶応出身だったせいだろうか。
何事も宿世(すくせ)の因縁なりかし、と悟りすました顔をするわけではないが、竹原 陽子さんからお手紙をいただいて、いろいろな人のことを思い出すことができた。
あれから数十年、もはや老いさらばえた私の肩にも、原 民喜がそっと手を置いてくれた重みが残っている。