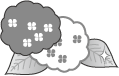1951年(昭和26年)3月16日、佐々木 基一の自宅で、原 民喜の葬儀が行われた。
当時、私は、肺結核にかかっていた。毎日、寝たり起きたりの生活だったが、この葬儀に列席するため、阿佐ヶ谷にむかった。
私が、佐々木さんのお宅に向かって歩いていたときのことも、『おお季節よ 城よ』のなかに書きとめておいた。
原の葬儀に出るために、阿佐ヶ谷の駅からぼんやり歩いていたとき、前方からきた若杉 彗(作家)が私の数歩前で立ちどまって帽子をとり、
「このたびは原君がほんとうに不幸なことになりました」
と丁寧に挨拶した。それまで若杉 彗と言葉をかわしたこともなかった。こちらがまるっきり無名に近い存在なので、若杉 彗が私を誰か別人と見間違えたのではないかとも思った。それとも私を「近代文学」の同人と知っていて挨拶してくれたのだろうか。私は深く頭をさげた。言葉は出なかった。ずっと年長の若杉 彗がわざわざ挨拶してくれたことに感動したのだった。 (「冬にしあらば」)
原の葬儀では、柴田 錬三郎、埴谷 雄高が弔辞をささげ、藤島 于内が、原さんの詩を朗読した。私は、佐々木さんのお宅の前の路地に立って、ひそかに涙を流した。
原 民喜の葬儀の日、作家の若杉 彗がわざわざ私に挨拶してくれた理由は、このときから私にとっては不明のままだった。
私は若杉 彗と直接面識がなかった。私のめざしていた方向とは、全く無縁の作家だったから、若杉さんと会う機会もないまま、原 民喜の葬儀の日、この作家が私に挨拶してくれたこともいつしか忘れてしまった。
これも数十年という歳月をへだてて、野木 京子さん、竹原 陽子さんの来訪を受けた。おふたりと別れたあと、あの原 民喜の葬儀の日、若杉 彗がわざわざ私に挨拶してくれた理由を考えてみた。
そして、何か思い出すかも知れないと思って古い写真を探してみた。
なにしろ古い話である。1949年(昭和24年)頃、私は埼玉県大宮市に住んでいた。
当時、1948年(昭和23年)頃、埼玉県の文化行政の部門が県内の文化人を集めて、懇親会のような行事をもったことがあった。ほとんど無名にひとしい私が招かれた理由は知らない。
この集まりに埼玉在住の文化人が多数出席したが、県庁側から、20代の若い女性が派遣されて、いろいろと対応してくれた。のちに歌人として知られる大西 民子女史だった。
このときの記念写真が出てきた。
いちばん若輩だった私は、埼玉県在住の文化人とはまったく交流がなかった。この席で、私に声をかけてくれたのは、詩人の秋谷 豊さんだった。その後も、秋谷さんは若輩の私に何度か手紙をくれたことがある。
この集まりで、大西さんは作家の竹森 一男さんを紹介してくれた。大西さんが若杉さんに紹介してくださったのではなかったか。失礼な話だが、当時の私は竹森さんの作品も若杉さんの作品も読んだことはなかった。なにしろ、頭のなかに、ドストエフスキ-、ジッド、ヴァレリ-しかなかった。はじめから、文壇などとまったく関係がないまま、もの書きになろうとしていた青二才にすぎなかった。
私は、若杉さんがどういう作家なのか知らないまま、ありきたりの挨拶を述べただけだったはずで、それ以後もまったく交渉がなかった。(後年、若杉さんは「エデンの海」を書いてベストセラ-作家になる。)しかし、若杉さんのほうは、若輩の私をおぼえていてくださったのだろう。
このときの記念写真を見つけた。数十名の列席者が並んでいるなかに、若杉さんの姿があった。私は、場違いな催しにまぎれ込んでしまったピエロといった恰好で、大西 民子女史の近くに立っている。
これではっきりした。
若き日の私が、若杉さんと面識があったということ。原 民喜の葬儀の日に、若杉さんは、トボトボと歩いている私を見て、声をかけてくださったに違いない。
この日の若杉さんの礼節は、私には忘れられないものになった。その後、私は、知遇を得た作家、批評家たちの葬儀に出て、面識のある人に会ったときは、かならずこちらから挨拶するようにつとめた。これも若杉さんから教えていただいたことだった。