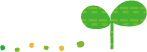私としては――妻の他界のあと、どういうものか自分の周囲のすべてが自分の内面の底に沈んでゆくような思いがあった。悲しみは深いものだったが、それは「さびしいんじゃなくて、むなしい。何をやっても」という思いではなかったか。どういうものか妻を喪った悲嘆までもむなしい。私がついぞしらなかった深淵が、ぽっかり口を開いている。そうなると、何もかもが、自分の知らなかった深淵に流れ落ちるようだった。私は何を考えているのか、何を書けばいいのか、わからなくなっていた。
知人たちから懇ろなお悔やみをいただいた。ほんとうにありがたいことだった。
そのありがたさをよそに、私は親しい友人たちに手紙も書かなくなっていた。何を書いてもあまり意味がない、という身勝手な気分のせいだが、友人たちも、そんな私の状況を察して、時候の挨拶や見舞いも遠慮しているようだった。
私はひたすら沈黙をつづけていた。
私を慰めるために、夫と死別した老女の聞き書きを贈ってくれた人もいる。その老女が語っている。(注)
お父さんが逝ってからのこの六カ月、みなさんがよく来てくださったから、ほん
んとうに助かったと思っています。いままで私はお父さんにずっと依存してきた
でしょ、不安だったの。
ひとり暮らしって、むなしいのね。さびしいんじゃなくて、むなしい。何をやっ
ても。一人でどう生きようかなって。一人で生きる自信もそんなにないし、と思
っていた。
(引用は――つぼた英子著、「ふたりからひとり」(編集・水野 恵美子/
自然食品社・2016年刊)による。
彼女のいう「むなしさ」は、肉親を失って残された「ひと」には共通する思いに違いない。私は「ひとり暮らし」ではないが、「さびしいんじゃなくて、むなしい。何をやっても」という思いは似ているだろう。私は、この本を贈ってくれた神崎 朗子(翻訳家)に感謝しながら読んだ。